■山田堰椅子時によりそう聖地、葬地の空間的特質に関する考察■
設計:城田和典
山田堰井筋とは、藩政時代、野中兼山の治水事業によって築造された山田堰より流れる上井、中井、舟入の水路のことである。水路は地域の農耕文化を支えるための豊富な灌漑用水を運び、地域住民の生活と連続的に密接な関係を持ち続けてきた。
また、絶え間ない水の流れは、川の流れを連想させるものであったのだろうか。ここでは、地域住民の特別な想いがあって、祠や神社など神を祀る聖なる場所が、水路という人工の構築物によりそう風景が生まれている。
そして、聖なる場所とともに、死者の場所である墓が水路に沿ってずらりと立ち並ぶ姿にも目を奪われる。水は命の根源であり、また、人の命を奪うものでもある。自然への畏敬の念のようなものをこれらの風景から感じ取ることができる。
現代に入ると、土木技術の進歩や市街化の拡大によって、コンクリート暗渠化に代表されるように水路の様態は変わりつつある。かつて水路は、水利を目的とする以上の意味が込められた特別な場所であったのではないだろうか。
本研究の目的は、山田堰井筋を事例として、水路によりそう聖地、葬地の空間的特質について考察すること、そして、水路の存在意義を解明することである。本研究では、水路周辺の地形や、水路周辺の村落という生活空間の領域と聖地、葬地の関連に着目して考察を行う。そして、地域住民にとって水路がいかなるものであるかを聖地、葬地という非日常的であり精神的意義の深い場所と結びつけて見いだしていくわけである。
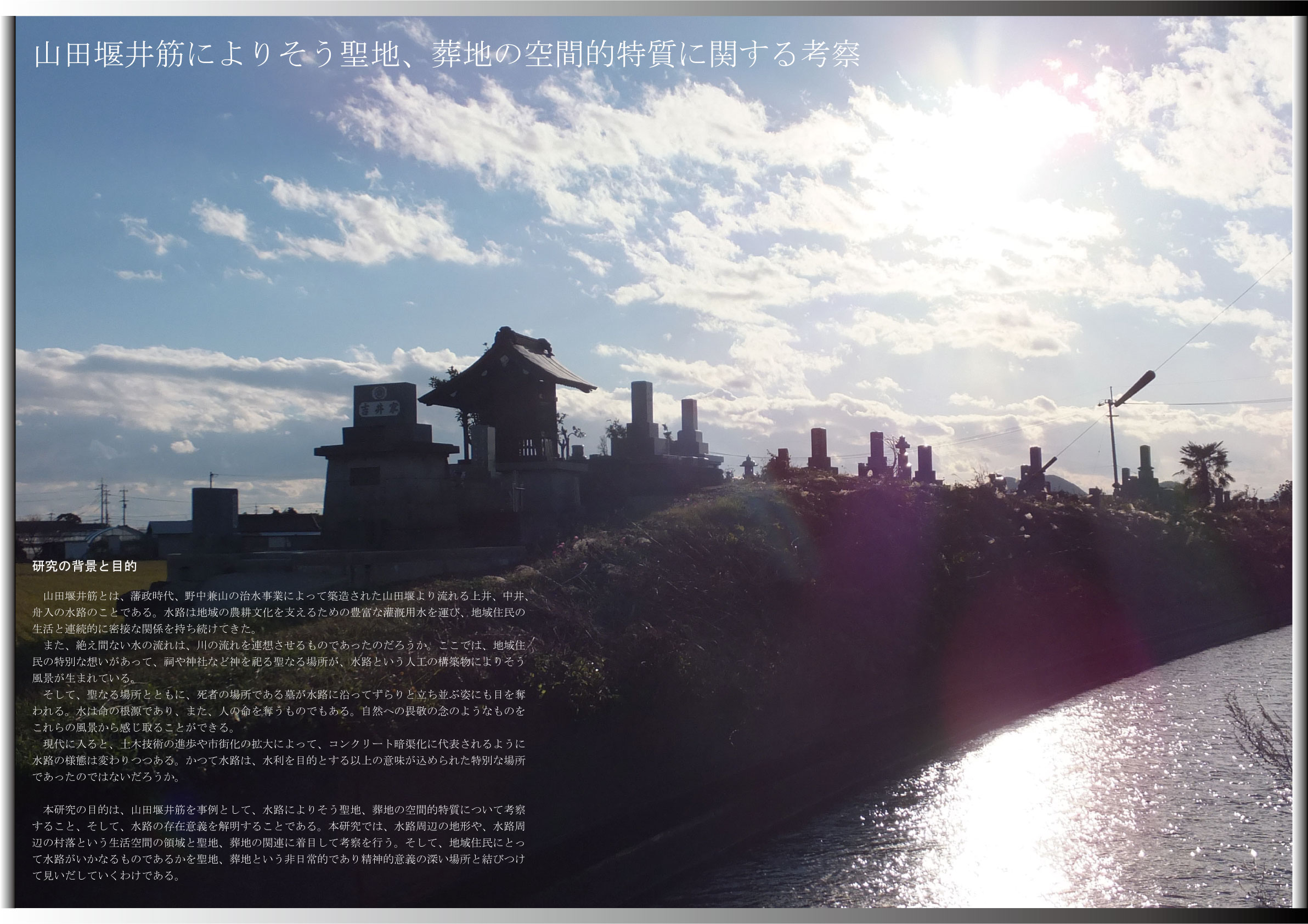
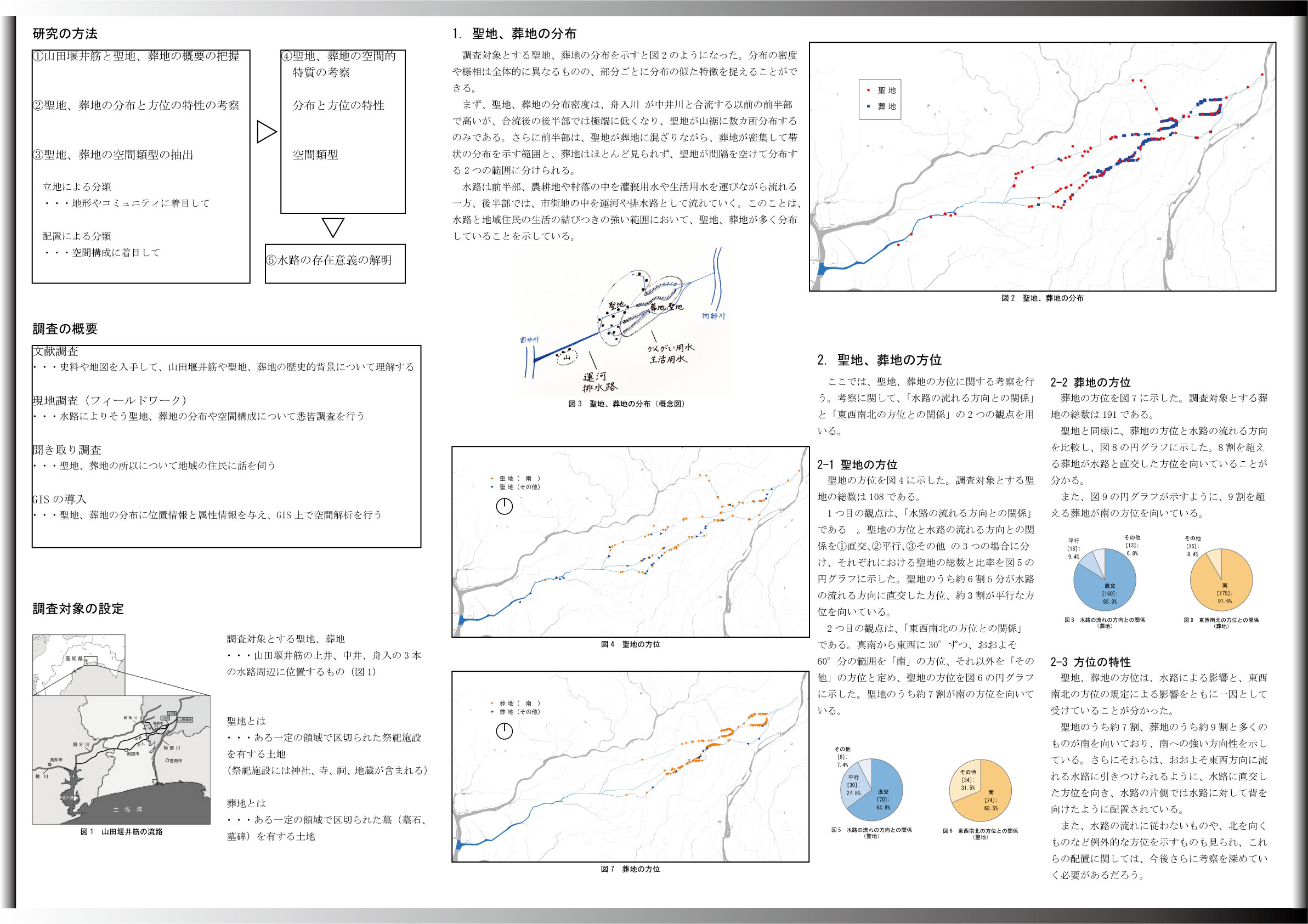
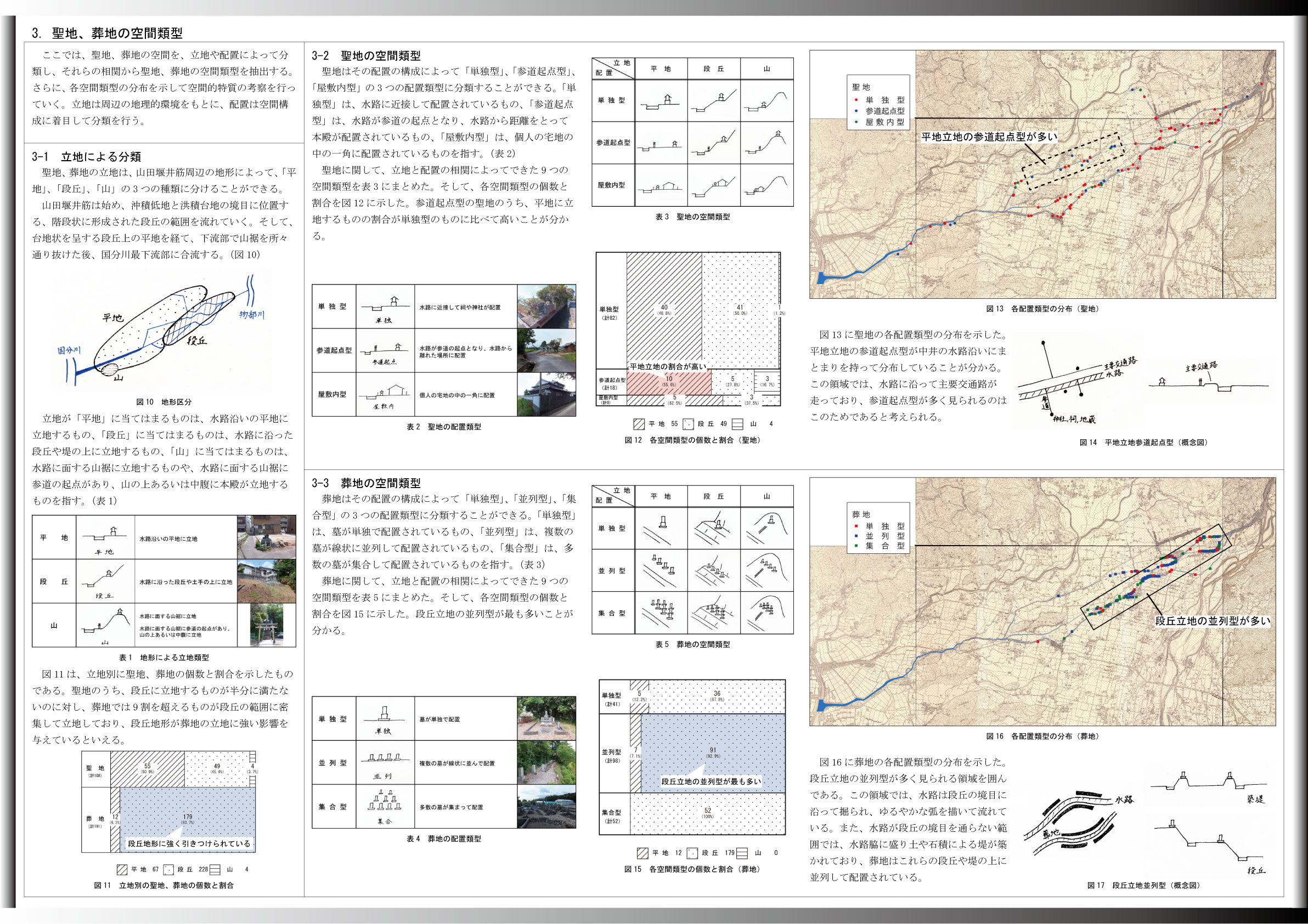

|